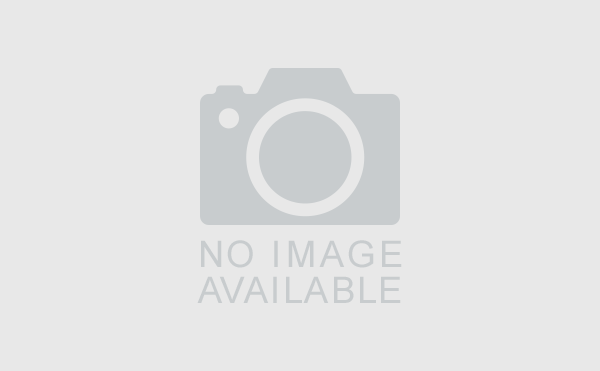【お知らせ】2025年第23回学術大会概要 12月6,7日
【お知らせ】2025年第23回学術大会概要 12月6,7日
開催概要
2025年12月6日(土) 9:30-17:00 学術大会1日目
午前/特別企画
午後/シンポⅠ(北京宣言)
17:30-19:30 懇親会
12月7日(日) 10:00-17:00 学術大会2日目
午前/個別報告、総会(西尾学術奨励賞受賞式含む)
午後/シンポⅡ(女性差別撤廃条約批准40周年)
(1)会場:津田塾大学小平キャンパス 1号館 所在地 東京都小平市津田町2-1-1
【主要路線からのアクセス】
・西武国分寺線 鷹の台駅下車、徒歩約8分。
鷹の台駅からの経路(Google Map)
・JR武蔵野線 新小平駅下車、徒歩約18分。
新小平駅からの経路(Google Map)
・JR 中央線 国分寺駅北口より西武バス( 武蔵野美術大学行 )約 12 分「 津田塾大学 」下車すぐ。
◆アクセスの詳細は、津田塾大学HP参照 https://www.tsuda.ac.jp/access.html
(2)参加申込 キャンパスに入構するための外来申請が必要なため、事前参加申込をお願いいたし
ます。詳細は、11月発行の大会プログラムでお知らせします。
(3)参加費 会員:参加費無料、非会員:大会2日間通して傍聴料1,000円
(学部学生以下500円、開催校・津田塾大学教職員・院生・学部生は傍聴無料)
(4)会場問い合わせ先:takeda@tsuda.ac.jp(武田)
(5)レジュメは、資料用ドライブに大会3日前までにおきます。会場での配付はありません。事前にダウンロードしてご来場ください。
(6)会場でのWi-Fi使用について お持ちの eduroamアカウントでご利用になれます。eduroamアカウントをお持ちでない方でご希望の方には、一時利用Wi-Fi(eventonly)のセキュリティーキーを当日受付でお渡しします。詳細は、11月発行の大会プログラムでお知らせします。
(7)昼食 昼食・飲み物については各自ご用意ください。教室や休憩室でご飲食いただけます。最寄り駅の鷹の台駅周辺にはコンビニや飲食店がいくつかありますが、とても限られています。日曜日は休みのところもあります。キャンパス周辺のコンビニや飲食店を参加者にはご案内いたしますが、あらかじめご準備をお願いいたします。
(8)一時保育 大会期間中(懇親会時は除く)、会員を対象として、一時保育を実施します。詳細につきましては、学会HPでお知らせしています【お申込み期限:10月28日(火)】。
(9)ジェンダー法学会学術大会参加のために学会当日に会員が外部で託児サービスを利用された場合は、予算の範囲内で実費の半額補助を致します。
① 外部の託児サービスを利用された場合は、学会当日ないし学会終了から3日以内に事務局宛に補助金申請をメールでお願いいたします(利用時間、料金、利用施設)。
② 領収書を郵送でジェンダー法学会事務局宛にお送り下さい(学会終了から1週間以内)。ご不明の点は、事務局までお問い合わせ下さい。
(10)学会参加者はそのお子さんを連れてシンポジウム等の会場に入ることができます。生後6か月~未就学児は一時保育もご利用いただけます。
(11)宿泊 宿泊については、各自で手配してください。予約が取りにくい時期もあります。早めにご予約ください。
(12)懇親会 事前参加申込をお願いします。詳細は、11月発行の大会プログラムでお知らせいたします。
(13)1日目午後および2日目午後のシンポジウムについては、会員を対象として、オンライン視聴を用意する予定です。実施および詳細につきましては、大会プログラムもしくは学会HPでお知らせいたします。
プログラム
2025年12月6日(土)学術大会1日目
9:30-11:30 特別企画 井田良講演(中央大学大学院法務研究科教授)
「強姦罪から不同意性交等罪へ—2017年・2023年改正の総括と積み残されたもの」
11:30-13:00 昼食休憩
11:40-12:30 第9期第8回理事会
13:00-17:00 シンポジウムⅠ 「北京宣言・行動綱領から30年――日本の現状と今後の課題」
(企画担当:川口かしみ理事、北仲千里理事)
(企画趣旨)
今年(2025年)は、第4回世界女性会議(北京会議・1995年)が開催され、北京宣言と行動綱領が採択されて30周年に当たる。北京宣言及び行動綱領では、スローガンとして「平等、開発及び平和のための行動」が掲げられ、行動綱領は、女性のエンパワーメントのために、12の重大問題領域(①女性と貧困、②女性の教育と訓練、③女性と健康、④女性に対する暴力、⑤女性の人権、⑥女性とメディア、⑦女性と環境、⑧女性の地位向上のための制度的仕組み、⑨女性と経済、⑩女性と武力闘争、⑪女性に対する権力及び意思決定における女性、⑫女児)におけるアジェンダが設定された。
報告書(Report: Women’s Rights in Review: 30 Years After Beijing, UN Women, 2025)によれば、1995年の北京宣言・行動綱領以降、たしかに女性の権利は教育や健康、法制度などの点では前進が見られた。しかしながら、国内では特にシングルマザーの生活困窮などや経済格差や政治など権力格差の点では課題が達成されていないままであり、また、TV局・タレント・映画演劇や自衛隊・米軍兵士による性暴力の問題もますます表面化してきたところである。それに加えて、今後は、女性の権利向上とインターセクショナリティ、平和と安全保障、気候正義(Climate Justice)等の視点も入れた議論・取組みや、デジタルテクノロジーによって引き起こされる問題の解決も求められていく。
そこで、本シンポジウムでは、現在までの国際状況や日本の状況から、北京宣言・行動綱領へのこの30年の日本国内の政策や社会変化において評価できる点、残された課題、さらに、新たな課題について検討する。
本企画は、ジェンダー法学会として初めて、この北京宣言と行動綱領を取り上げるものである。
(構成)
司会 川口かしみ(宮城学院女子大学)、北仲千里(広島大学)
1 企画趣旨 川口かしみ(宮城学院女子大学)
2 大崎麻子(特定非営利活動法人Gender Action Platform理事、第69回国連女性の地位委員会(CSW)日本代表・非会員) 北京+30レビュー:国際的評価と日本への示唆
3 大沢真理(東京大学名誉教授・非会員) 国内の現状と課題―貧困・格差を手がかりに
4 細谷夏生(弁護士・会員) セクシャルハラスメントへの司法的対処:北京宣言・行動綱領30年の軌跡と現在地
5 長島美紀(公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン アドボカシーグループリーダー・会員) 気候変動とジェンダーの交差点に立つ若年女性:日本における調査実践と制度的課題の検討
6 河村有教(長崎大学・会員) AI・テクノロジーとジェンダー―デジタル性暴力とその規制を中心に―(仮)
5 ディスカッション
6 質疑応答
17:30-19:30 懇親会 会費:6000円(院生4000円)
2025年12月7日 (日) 学術大会2日目
10:00-11:00 個別報告 「人工妊娠中絶の決定過程における男性の関与の構造と制度的課題 ——配偶者同意要件の解釈・運用と制度再構築に向けて——」 新山惟乃(お茶の水女子大学大学院)司会:島岡まな (大阪大学)
11:10-11:40 第23回 総会 (西尾学術奨励賞受賞式含む)
11:40-13:00 昼食休憩
11:40‐13:00 若手企画
13:00-17:00 シンポジウムⅡ 「女性差別撤廃条約批准40周年を迎えて:SRHRから考える条約のこれから」 (企画担当:藤本圭子理事、谷口洋幸理事)
(企画趣旨)
日本が1985年に女性差別撤廃条約を批准してから、今年で40年を迎える。この間、政府は条約の履行義務を果たすべく、国内のジェンダー関係の法政策も見直してきた。その過程では、国家報告制度を通じた女性差別撤廃委員会との対話も重要な役割を果たしてきた。
一方で、同委員会から複数回にわたり同内容の勧告が繰り返されるなど、依然として国内の女性をめぐる人権状況に変化が見られない課題や、新自由主義の台頭以降において、法政策が後退していく兆しもある。また政府において、条約の意義を十分に認識せず、そのプロセスを軽視する傾向も見受けられ、本年1月には任意拠出金の使途から同委員会を除外することを伝達するといった出来事もあった。
本シンポジウムでは、過去40年の経験を振り返りながら、女性差別撤廃条約の意義を再確認し、同条約をより有効に活用するための方策を探る。特に、長年議論されつつ、バックラッシュの格好の標的となりうるSRHR(性と生殖に関する健康と権利)に焦点を当て、今後の展望を考える。
(構成)
司会 藤本圭子(広島弁護士会)、谷口洋幸(青山学院大学)
1 企画趣旨 谷口洋幸(青山学院大学)
2 基調講演 山下泰子((文教学院大学大学名誉教授・会員) 女性差別撤廃条約と日本の40年
3 報告者1 鈴木裕実(仙台弁護士会・旧優生保護法国賠訴訟弁護団員・非会員) 女性差別撤廃条約と旧優生保護法国賠訴訟
4 福田和子(#なんでないのプロジェクト代表・東京大学多様性包摂共創センター特任研究員・非会員) SRHRと第6回審査
5 報告者3 谷口真由美(神戸学院大学客員教授・会員) SRHRの今までとこれから
6 質疑応答
7 総括コメント 谷口洋幸(青山学院大学)